ハヤカワ新書4月刊ラインナップ紹介『「痛み」とは何か』牛田享宏、『行動経済学の死』川越敏司、『立ち読みの歴史』小林昌樹
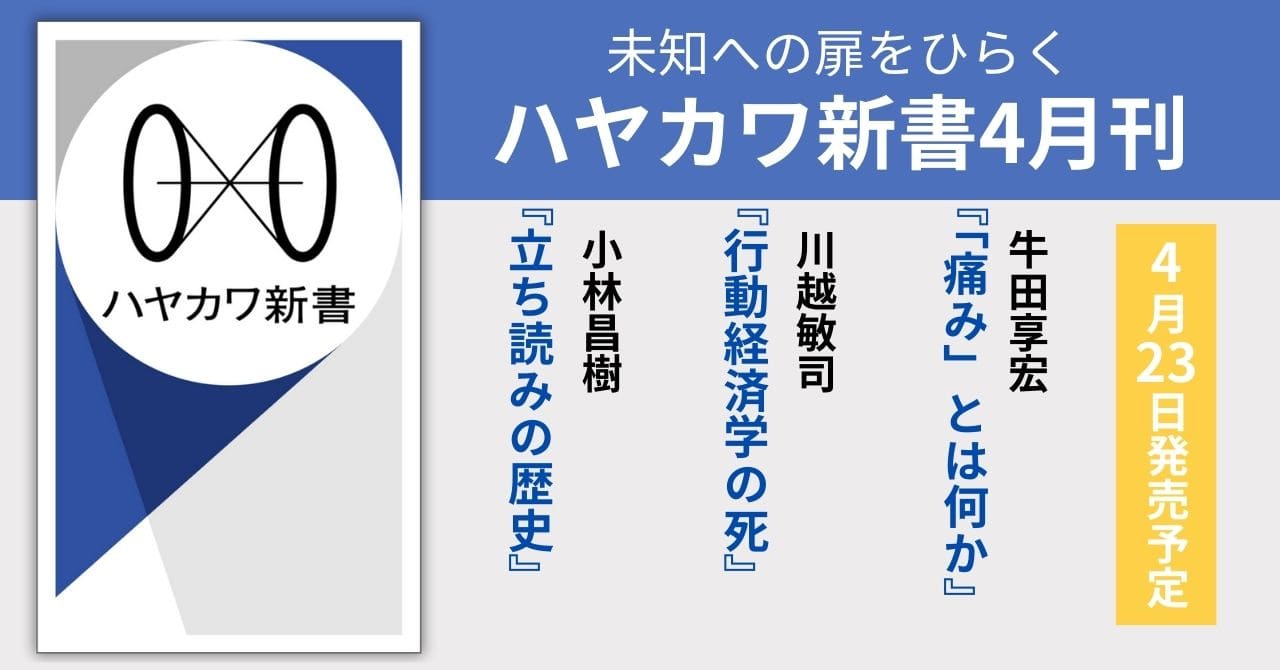
ハヤカワ新書の最新刊は、2025年4月23日(水)発売予定です。ラインナップと内容をご紹介します。
①『「痛み」とは何か』牛田享宏
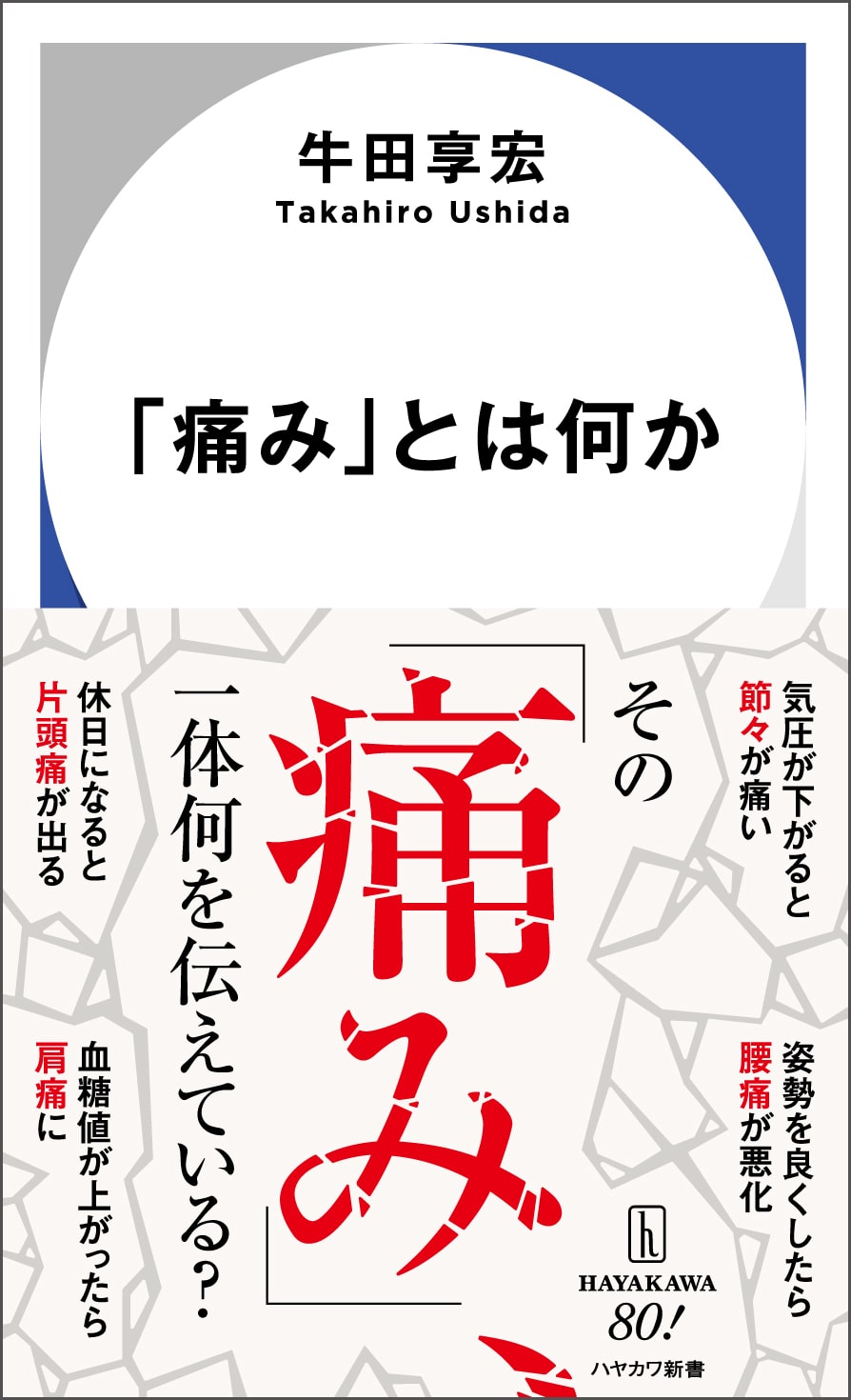
【内容紹介】
腰痛や膝痛、肩痛など何らかの痛みを抱える人は全国で約二〇〇〇万人。身近な「痛み」だが、「ヘルニアを取り除いたはずなのに痛みが続く」「ケガの箇所を安静にしたらかえって痛みが悪化した」など、謎の症状に悩まされることも。さらには、幼少期の親子関係や職場の人間関係など、意外な要因が痛みの背後に潜むケースまで。痛みの専門医として、全国から訪れるさまざまな患者を診察してきた斯界の第一人者が、最新の治療法や研究成果を踏まえ、体と心に秘められたミステリ「痛み」の真犯人に迫る。
【著者略歴】牛田享宏(うしだ・たかひろ)
愛知医科大学医学部教授。慢性痛に対し集学的な治療・研究を行なう日本初の施設「愛知医科大学疼痛緩和外科・いたみセンター」で陣頭指揮を執る。1966年生まれ。高知医科大学(現高知大学医学部)を卒業後、 テキサス大学客員研究員、ノースウエスタン大学客員研究員などを経て現職。国際疼痛学会の痛みの定義作成メンバーであり、厚生労働研究班の班長として「慢性疼痛治療ガイドライン」を作成するなど日本の痛み治療をリードする存在である。
②『行動経済学の死』川越敏司

【内容紹介】
経済学に心理学の知見を取り入れ、新たな地平を切り拓いた行動経済学。「ビジネスに役立つ」と脚光を浴びる一方で、実はその成果に疑惑の目が向けられている。損失回避性などの主要な主張には根拠が乏しく、行動変容を促すナッジにも効果がないとする批判だ。心理実験を中心に「再現性のなさ」が問題視されるなかで、行動経済学はもはや学問として「死」を迎えているのか。行動経済学会・会長が、歴史的経緯から最新研究まで踏まえ、徹底検証。真相を解き明かし、その学問的意義をとらえ直す。
【著者略歴】川越敏司(かわごえ・としじ)
公立はこだて未来大学システム情報科学部複雑系知能学科教授。行動経済学会会長。大阪市立大学大学院経済学研究科前期博士課程修了、博士(経済学)。1970年、和歌山県和歌山市生まれ。埼玉大学経済学部社会環境設計学科助手等を経て、2013年より現職。専門分野はゲーム理論・実験経済学。趣味はバロック・フルート演奏、チェス・プロブレムや漢詩の創作。著書に『行動経済学の真実』(集英社新書)、『実験経済学』(東京大学出版会)など多数。
③『立ち読みの歴史』小林昌樹
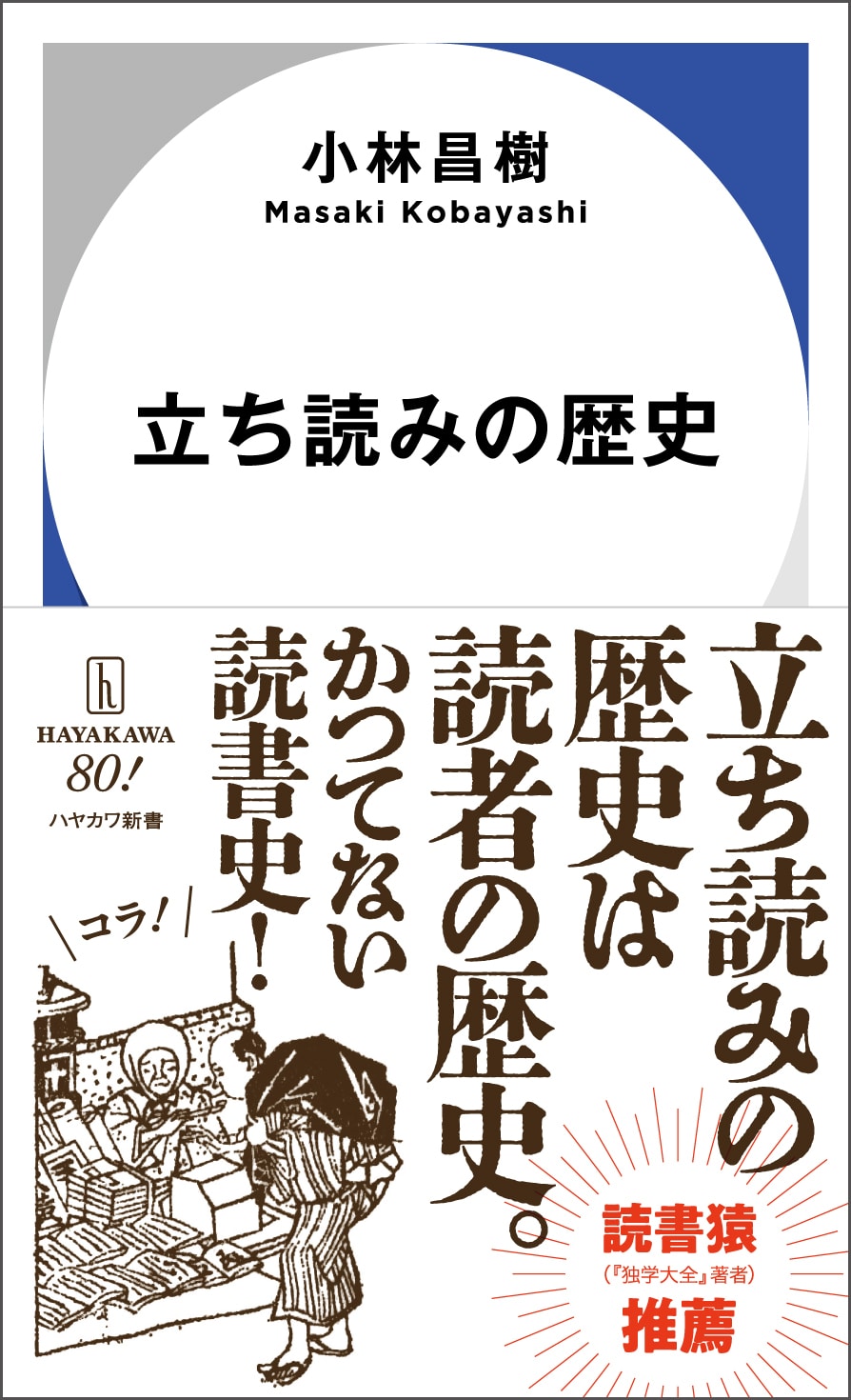
【内容紹介】
かつて洋行知識人は口々に言った――「海外に立ち読みなし」。日本特有の習俗「立ち読み」はいつ、どこで生まれ、庶民の読書文化を形作ってきたのか? 本書はこれまで注目されてこなかった資料を発掘し、その歴史を描き出す。明治維新による「本の身分制」の解体、ニューメディア「雑誌」の登場、書店の店舗形態の変化……謎多き近代出版史を博捜するなかで浮かび上がってきたのは、読む本を自ら選び享受する我々「読者」の誕生だった! ベストセラー『調べる技術』著者がその技を尽くす野心作。
【著者略歴】小林昌樹(こばやし・まさき)
1967年東京生まれ。図書館情報学を研究するかたわら近代出版研究所を主宰し、年刊誌『近代出版研究』編集長を務める。慶應義塾大学文学部卒。国立国会図書館で15年にわたりレファレンス業務に従事、その経験を活かした『調べる技術』が3万部を超えるヒット作となる。その他の著書に『もっと調べる技術』(以上皓星社)、編著『雑誌新聞発行部数事典』(金沢文圃閣)、共著『公共図書館の冒険』(みすず書房)など。コミケにも精力的に出店している。